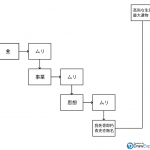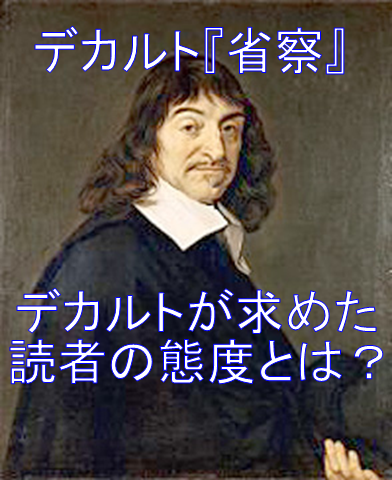堀尾輝久という教育学者は、日本の戦後の教育学においてとてつもなく大きな役割を果たしました。
政治学者丸山真男・教育学者勝田守一に師事し、主にコンドルセを中心とした、近代フランスにおける教育思想の知識を基軸にして、現代の教育について論じています。
おそらく大学の教職課程における教育史といった基礎科目、あるいはゼミナールにおいて、堀尾輝久は日本の教育学研究史の文脈において、ほとんど確実に扱われます。
『現代教育の思想と構造』(同時代ライブラリー)は、堀尾氏の代表作であり、博士論文を再構成して出版されたものです。言うまでもなく丸山真男氏の代表作『現代政治の思想と構造』をもじったものです。(堀尾氏のタイトルを見て、丸山氏がどういう反応を示したのか気になるところではあります。)
この少々難解な本を読むためのガイドとして、ポイントを私なりにまとめてみました。
下記クリックで好きな項目に移動
『現代教育の思想と構造』目次
目次としては以下のようになっています。
第一部
第一章 近代教育の理念と現実―公教育思想を中心として
第二章 独占=帝国主義段階における教育―「国民教育」の成立を中心として
第二部
第一章 教育を受ける権利と義務教育―親権思想の変遷を手がかりとして
第二章 「教育と平等」をめぐる問題―教育の機会均等論批判
補論 国民教育における「中立性」の問題
今回は、第一章をまとめてみたいと思います。読むポイントと思われる箇所を、箇条書きにしてみました。
第一章 近代教育の理念と現実―公教育思想を中心として
・公教育の国民的規模での成立は19世紀末以降。
・理念とは近代社会(古典的市民社会)の理念から論理内在的にみちびかれる教育理念(原則)を意味する。
・現実とは、実際の市民社会の資本主義体制が、ある種の教育を必要としたこと、またそれを支えるための思想を生み出したこと。
・現実が要請する思想と、市民社会の論理内在的にみちびきだされる思想とを厳密に区別する必要がある(イデオロギーとユートピア)。
第一節 問題設定
・公教育の意義の評価が、概して教育機会の拡大という量的側面に目を奪われ、その質の検討は十分になされていない。
・近代教育の理念と、実際に生み出されて行われている現実の教育には、ギャップがある。
・ユートピアと現実のイデオロギーの交錯を解きほぐす過程で、多様な公教育の思想の、それぞれの本質をとらえ、その位置づけ(構造づけ)を行う。
第二節 市民社会における教育体制
・古典的近代のエートスは人権宣言に結晶している。人権は、自然法に基づく人類普遍の原理に高められた。
・ところが、この理念に反して、現実の第三階級のブルジョワジーによる市民革命(「第三階級とはすべてである」(シェイエス))は、自己との対立物である第四階級の非存在、人権の主体から外すことを意味していた。そのことによって、市民社会の理論の普遍的性格は喪失し、その形式的普遍性は、資本主義の対立的現実を隠蔽するためのイデオロギーに転化した。
・理念と現実の矛盾の解決はシェイエスの区分によってなされる(『第三階級とは何か』)。第三階級=能動的公民、第四階級=受動的公民。すなわち、資本主義における労働者=経済的には労働力(商品)、政治的には統治の客体、社会的には社会のかすとして非人間的存在、非存在。
・このような理念と現実の錯綜した教育組織は三重構造である。一つは、第三階級以上の支配階級の自己教育。もう一つは、労働者大衆の教育組織。後者がさらに、二種類の異質な組織に分かれる。その一は、支配階級による労働者大衆の「教化」の組織であり、その二は、労働者の階級的自覚を前提とする労働者の自己教育の組織である。
第三節 市民社会の理念と近代教育原則
・理念からみちびきだされる教育原則の本質を整理し、それがどのような公教育論を成立させているかを明らかにする。
一 近代教育原則
・近代教育思想の本質的な部分の整理。
(1)人権思想の系(コロラリー)としての子どもの権利の確認と、その教育的表現としての学習権ないし教育を受ける権利の主張。
(2)近代的親権観の成立により、親は、子どもの権利を実現させるための現実的配慮の義務を負い、この子どもにたいする義務を第一次的に履行する権利をもつ。この権利は、親の自然権に属する。
(3)近代における人間(l’homme)と公民(citoyen)の区別に対応して、教育の目的は、公民の育成ではなく、人間の形成におかれた。教育(l’education)という言葉は、人間の内面形成、とりわけ徳性の涵養を中心とする全面教育を意味し、知育(l’instruction)とは区別されて、より重要なカテゴリーであった。
(4)人間の内面形成にかかわる問題は、国家権力の干渉してはならない「私事」とされた。
(5)以上の原則から必然的に、国家が教育を主宰し、指導することは、自己の任務の限界をおかすものとして否定された。
(6)その結果、公教育は、国家が全面教育をひきうけ、人間の内面にまで立ち入ることになるかぎり否定された。
(7)教育方法は、子どもの権利の確認と並行して、子どもの自発性が尊重され、つめ込み主義が否定された(消極教育l’education negative)。
(8)これらの諸原則を生かすための教育形態としては、家庭で親や家庭教師による個人指導が理想とされた。
・この整理の参考は、コメニウス、ロック、ルソー、コンドルセ、ペスタロッチ、フンボルトなど。「古典的市民社会」の理論に矛盾しない思想をとりだした。
二 近代教育原則と公教育
・とはいえ、学校は現実的には必要だった。その現実的条件とは、一般的には、教育のある部分は、学校に任せたほうが有効だという認識。特殊的には、「原始的蓄積」の家庭で、貧困によって教育どころか生命さえ危ない子どもが多数いる事実。
・こうして学校の存在を媒介にして、近代教育の原則がどのように生かされうるかが、近代教育思想の新しい課題となる。
・近代(教育)思想は、自然法的・普遍的性格が特色。
・近代教育思想(原則)と内的連関をもった公教育思想はどのようなものか。コンドルセ(1743-94、親ジロンド派)の公教育論:(権力からの)独立論と(機能の)限定論
(1)すべての人間に、教育を受ける権利を認めた。平等主義・普遍主義が、彼の公教育論の前提。
公教育は家庭教育の延長であり代替物であり、偏見をなおすための集団化(親義務の共同化)として構想されている。したがって、就学を強制しない。
「親の自然権(教育義務)」思想と、「新しい世代(子ども)の権利」を柱とする、教育の公権力からの独立論。
(2)公教育それ自体の限定論。
教育とは徳育を中心とする人間形成。公教育が人間教育のすべてを引き受けるのは、「良心の権利」に反し、親の自然権を犯すことになる。なぜなら、
親はその自然権を公教育に全面的にゆだねたのではないから。
こうして教育(徳育)と知育が区別され、公教育は後者に限定される。宗教・道徳教育が除かれ、世俗主義(laicisme)が要求される。
・教育形態が、私的な家庭教育から公立学校へその比重を移したことは一見重大な変化に見える。しかしコンドルセの理解を通せば、近代教育思想の具体化でありその展開にほかならなかった。すなわち、
(1)学校は家庭の延長であり、機能の代替であり、私事の組織かであり、親義務の共同化(集団化)であった。
(2)公立学校は「権利としての教育」の思想を、普遍的に現実化するためのもっとも有効な手段であった。
(3)教育(徳育)と知育の区別の視点が出た。
(4)3がさらに教育と学校教育を区別する考えを成立させた。
(5)同じ根拠で世俗主義の原則が提示された。
(6)権利だから、無償教育と就学非強制の原則。
・以上6つが近代教育原則といえる。
・モンタニャール(山岳派・ジャコバン派・左派。ロベス・ピエール、ダントン、マラ)では、「子どもたちは、両親に属する前に共和国に属する」(ダントン)とされ、ここから公教育の義務制が基礎づけられる。
第四節 市民社会の現実と大衆教育の思想
*ここから現実の話。
一 資本主義の発展と大衆教育の必然性
・資本主義体制は教育への国家介入を要請し、一つの公教育観を成立させた。
・一般に、この「公教育」(労働者大衆の教育(教化)。つまり現実の方)が近代教育としてとらえられ、近代教育史の主軸とされる。では現実の要請するイデオロギーとは何か。
・産業資本主義の歴史は、成長期と確立期に分けられる。
・成長期には、産業資本家たちは、教育にたいして熱意を示さない。教育を与えることは、秩序を乱すと考えられた(マンデヴィル、1670-1733。イギリスの医師・モラリスト、『蜂の寓話、または個人の悪徳は社会の利益』)。
・なぜなら、分業制と機械の導入は、単純労働を可能にし、ここから安価な児童労働を大量に取り入れた。学校に行く時間は労働時間の減少である。
・これに対応して「慈恵教育(チャリティ・エデュケーション)」の誕生。博愛主義者や没落貴族、国教会の旧勢力が、失地回復の意図を含めて構想した。目的は治安維持と犯罪予防。したがって内容は宗教中心の道徳教育。従順な賃労働者の育成に役立つ。資本家と利害が一致。
・慈恵教育が国民教育制度の出発点として評価されるが、実体はそうではない。
・確立期は18世紀後半から19世紀前半。1830年代は産業革命の終結と、ブルジョアジー勝利の年。大衆教育のイニシアチヴが旧勢力から新興ブルジョワジーの手に次第に移り、徐々に大衆の教育機会が拡大。工場法における就学義務規定の拡大により、工場学校(factory school)が誕生する。
・新興ブルジョアジーたちの、教育は秩序を乱すという従来の認識は徐々に変わり、教育(道徳)こそ治安維持に必要だと考え始める。この認識の変化はマンデヴィルの教育危険視(『蜂の寓話』1714)からスミスの教育有効説(『国富論』1776)への転換に象徴されている。
・労働時間を減らさず、宗教=道徳教育(カテキズム)を中心とする日曜学校が急速に発展。教育によって児童は予想以上に従順になったのでブルジョワジーも支持した。とはいえ教育を与えすぎるのも危険。
・このような支配階級の教育要求が、教育内容を規定する。「限定づき教育」は、カテキズムを中心とする宗教=道徳教育に象徴される。宗教教育の社会的効果は、「教会と国家の支配者に対する服従の基礎を子どもの精神に植えつけ、神意がかれらに与え給うた地位に満足し、かれらの激情を鎮め、尊敬すべき有徳なひとびとの地位を守るのに役立つ」ことにあった。これが本質。(D.ウィルソンの発言)この考え方はイギリス初等教育の歴史を一貫している。
・「限定づき教育」が、自己の論理を裏切るものであると同時に、労働力の保全という産業資本の本質的要求に合致するものであった。
二 資本主義的現実に応える公教育思想
・近代教育思想の理念とは別に、現実の資本主義が要請するイデオロギーが必要。この二重構造の原型はロック Plan for Working-School for Poor Children, 1696に見られる。「自己教育の原則」にとっては例外的な措置。大衆教育は原則に対する例外。
・アダム・スミスの公教育思想:3R’s(読み・書き・算)の奨励(強制してもいい)=文盲からの解放のもたらす道徳的効果に期待。治安維持のための道徳=宗教教育。
・マルサス:スミスの思想を、救貧制度廃止論として展開。人口理論によれば、貧困は無知と悪徳に起因する自己責任。貧困からの解放の道は、勤勉と節約と道徳的抑制以外にないことを学ぶ必要がある。救貧ではなく教育が強調される。
・ベンサム:「パノプティコン」(円形建築・刑務所)と名付けた大衆教育の学校=道徳教育。ブルジョア階級のための「クレストマスィア」=実学、宗教=道徳教育は除かれた。
・大衆教育の領域では、国家ないし公的機関の介入が肯定、内容は宗教=道徳教育を中心とし、秩序維持、犯罪予防の目的をもつ。従順な労働力を育て、革命や社会不安を防止する(労働力の保全)という産業資本の要求に応じるものであり、教育制度の二本建て(複線型)は階級分裂に対応。
・ふたつの例外。自己教育の原則に例外(教育を教化に変質)。同時に「レッセ・フェール原則」(救貧や警察への公費支出を減らすための国家介入)にも例外。
第五節 労働者階級の自己教育思想
・チャーティズムへの不満。宗教=道徳教育中心で、科学的知識を重んじていない。
・自己教育の必要性を認識し、大衆教育のヘゲモニーを自分たちで握ることを考えだす。
・ホジスキン(1787-1869、イギリスのリカード派経済学者)の主張「ひとはその教育を、自分の主人たちから受けるくらいなら、教育を与えられない方がましだ。なぜなら、そのような教育は、くびきにつながれてだめにされる家畜の訓練よりもよくはないからだ」
・自己教育は「権利としての教育」の思想の直接的表現。教育の機会の増大を求め、公費教育の構想がなされる。
・この公費教育は、無償制・世俗性を要請する。政治宗教の排除、内面の自由。
第六節 公教育概念の再吟味
・19世紀後半以降の帝国主義国家での「国民教育制度」の成立は、基本的には、ナショナリズムを主柱とする「教化」組織だった。
・近代教育のエートスは、労働者の自己教育思想に継承され、現代教育の思想は、市民社会の例外として認められた事実と、そのイデオロギーの、延長線上での新たな展開だといえる。
・多様な公教育に共通しているものは、
(1)対象が労働者大衆の教育である。
(2)国家ないしは公的機関がなんらかの仕方で関係している。
(3)目的がなんらかの意味で公的なものを含んでいる。
(4)公費教育ないしは、公立学校制度を建て前とする。
・しかしこれらは公教育の本質を規定したことにはならない。コンドルセのように近代教育の原則(私事性)そのものも、ひとつの公教育思想を成立させていた。
・したがって、公教育という言葉は、ほとんど何も限定していない。
・ただ、公費教育ないしは公立学校教育は、それ自体の意味と内容をもっている。
・したがって、多様な公教育の質を規定する一つの基準は、それがどのような公費観をもっていたかということと密接に関わる。
続き(第二章)はこちらから。
文献はこちら。