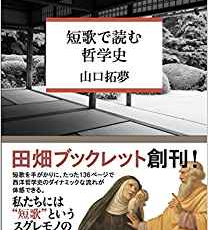田川建三の著作は非常におもしろいです。宗教に少しでも興味のある方は、読んで損はないかと思います。
中でも『宗教とは何か』という著作は、宗教学者の方も、宗教学入門として真っ先に勧める本です。
田川建三、『宗教批判をめぐる 宗教とは何か(上)』、洋泉社MC新書、2006年(1984年) ★
(古書店で見つけたら、すぐに買うこと。そして、三「「近代の克服としての宗教」批判 ─宗教学という逆立ち─」を必ず読むこと。)
今回は、その第3章である「近代の克服としての宗教」批判 ─宗教学という逆立ち─を読んでいきたいと思います。
(※以下、文中に頻出する「……」は、中略の意味。見出しは独自に付加。)
下記クリックで好きな項目に移動
田川建三「近代の克服としての宗教」批判の抜粋
宗教を近代の否定もしくは克服として担ぎ出す考え方自体が……近代合理主義の申し子なのであり……むしろ近代合理主義を補完するものこそが、そういう形でとらえられた宗教なのです。
宗教学の発生は帝国主義に由来
宗教学は、特にキリスト教とか仏教の研究を意識して避けて通っている学問だ……宗教学が誕生しましたのは……キリスト教神学に対するある種の反発として生れたわけです……帝国主義の時代、つまり、十九世紀後半です……「宗教学」ははじめから西洋世界の帝国主義的な拡張という歴史に刻印を押されているというその関係は、押さえておく必要があると思います。
宗教学の成立に関して、一番大きなきっかけを与えたものが特にインドの宗教です……宗教の比較をこととする学問が始まったのです……もはやキリスト教だけが唯一の真の宗教というようなことは言えなくなってしまったけれども、それをなおかつ、がん張って無理をしていたのが初期の西洋宗教学です。
そこで二つの傾向が現れたわけです。一つは、当時流行の進化論を宗教に適用していった……キリスト教が宗教の発達のつきつめた頂点だという考え方です……宗教の出発点はアニミズムなんですよと、それがだんだん発達して、ここまで行くんですよという理論……しかしすべての人間の宗教的ないとなみが同一の「原始的なもの」から出発しなければならない、と考えるとすれば、これはもはや、事実の認識なんていうことでなくて、イデオロギーです。
もっとも、宗教学者の方もこれほどに安直な理論を提出しているわけではなく……もっと抽象的に「宗教」の最高形態を考えるのですが(そしてこの抽象性こそ近代科学の発想の一つの特色ですが)……こういう理論には無理が行くということが容易に目に見えるので、ある程度行くと放棄されるわけです。そこで今度は逆にひっくり返した理論が出てくるわけです。つまり、一番原始的な宗教こそ唯一絶対神に対する信仰を必ずはらんでいるんだ……という思想です。
啓蒙主義から近代宗教学へ
結局、その中で今日に至るまで生き残っている考え方は何かといいますと……一番根本には「宗教そのもの」があるんだという考え方です……なんとなく曖昧に「宗教的なもの」としておくわけです……まさに近代科学の発想そのものなのです。すべてのものに同一の基本的原理が存在する、という。
(この)発想は、啓蒙主義から出てきている……(啓蒙主義は)キリスト教に対する反発として言われていたわけです……が、この段階の宗教論は宗教を「上」から引きずりおろすことにのみ懸命で、その結果逆に、人間性を抽象性の高みへと追い上げてしまったのです。
つまり、どんな人間も必ず同じように「宗教的なもの」をつくり出すのだというのが「普遍的な」法則です。どんな人間も必ずというのは、まさにどんな歴史的社会的状況であろうとも必ずというのだから……それがもともと生きていたその現実状況から抽象されてきてしまう。つまり非常にはっきりした抽象性です。
(19世紀後半に生まれた)新しい学問である近代宗教学は、啓蒙主義の宗教観を出発点として持ちながらも、それを克服したところで成立したものだ、ということが普通言われておるわけです……つまり「宗教的なるもの」とは、むしろ理性を超えた何かあるもの、人間の目にはむしろほとんど非合理的なものとさえ見えるもの……不可解なもの、恐ろしいものというような形で把握した。
現代宗教学は啓蒙主義的な視点を克服したと称しておいでだけれども……実は基本的な姿勢は同じなのです……つまり克服したのではなく、言い換えたにすぎない。根本的に言って、普遍性と抽象性という点では全然変っていない……抜き出してきた抽象物にどう色を塗るか、というだけの違いです。
宗教学=「宗教そのもの」なる概念の前提
フリードリッヒ・ハイラー……『祈り』という表題の有名な書物を書いていますが……「宗教学は……個々の宗教や宗教的人格(イエスとかパウロとか親鸞とか日蓮とか……)を扱うのではない。宗教そのものを扱うのである」、とおっしゃっています。「宗教学」と称しながら、自分たちは絶対に、個別具体的に存在している諸宗教なんぞ研究の対象にしないよ、とうそぶいておられる……そういう「宗教そのもの」なるものをまず前提してかかる。その前提の上に立って、では「宗教そのもの」とは何か、と問うわけです……自分でたてた前提を結論においてくり返しているにすぎません。
マックス・ミュラーという人……この人も典型的に啓蒙主義の宗教理解の発想を引きずっている……(啓示宗教と自然宗教という二つの概念について)「要するにまず宗教という基礎がなければならない……この基礎そのものを自然宗教と名づけるならば、どんな啓示宗教であろうともなんらかの形で自然宗教の岩の上に建っていると言える」というふうに定義しています。……彼は、その「自然宗教」なるものを、「非合理的」なもの、ないし「不合理的なもの」とのかかわり、なのだと説明します……その意味で啓蒙主義の宗教観を克服したと言われているわけです。けれども、まさに歴史的社会的人間的諸現実に関係なしに、すべての人間に共通する「宗教」なるものを想定している、という点では啓蒙主義の宗教観の継続にすぎません
エリアーデ批判
エリアーデが要するに何を継承したかと申しますと……ルドルフ・オットーの『聖なるもの』という書物がございます……すべての人間に何か宗教的なものが共通して存在しているのだ、と考え、それを「聖なるもの」と名づけるわけです……オットーは、近代宗教学の考え方(中性的普遍性)にキリスト教的な絶対性(「聖なる」)をひきずりこんで接ぎ木したのです……カール・バルトの「絶対他者」は男性ですが、オットーの絶対他者は中性です……エリアーデはオットーのこの考え方をひっぱりこんで、これをもう一まわり現代風に焼き直ししたのです。
この人(エリアーデ)がずるいのは、オットーという男はそれでも自分なりに、何とかそれ(聖なるもの)を明晰に示そうとしていろいろ努力しているのですが、エリアーデの方は、これをすべての宗教の基礎にあるものとして、何の説明もなく、当然の如く前提してしまっている点です。
この種の宗教思想においては、「聖」こそが人間にとって真実の事柄である、と考えるので、そうだとすれば、それが「本当の現実」である、ということになる。従ってその裏返しとして、「俗」すなわち人間の現実の生は、本当の「現実」ではないのだから、「非現実」……「観念」「仮想」にすぎない、ということになってしまう……人間のつくり出した宗教的観念が人間にとって真の「現実」となり、人間の生きた現実がただの「観念」とみなされるようになる。こうして宗教思想においては観念と現実が逆転してしまう……たとえそれが逆転した虚妄な思想であっても、パウロなどはそれなりにその方向で徹底して問いつめようとしている。それに対してエリアーデは、そういう発想を手軽に借りてきて言葉を並べているにすぎない。
エリアーデの特色がどこにあるかと言うと、古代人といわゆる原始人は「宗教的人間」なので、「聖なるもの」の実在を常に意識して生きていたのだが、現代人は「聖なるもの」を失った世界に生きている、と言うのです……現代人もそういう感覚をとりもどそうではないか、と説教しているわけです……そこでエリアーデとしては……古代人やいわゆる原始人の行動の中に、何でもかでも「聖なるもの」の顕現を読みとればいい、というわけです。
「アルンタ族のアチルパ人の伝承によれば……ヌンバラクによって秩序づけられた宇宙」……てな調子で、聞いたこともないような知らない固有名詞ばかりを並べられると、何となくひどく実証的みたいな感じがしてきてしまうのです。エリアーデの書物はいずれもそういった古代人やいわゆる原始人の実例をつぎからつぎへと百科辞典的に列挙していくだけであって、ただ最初の頁と最後の頁に、だから「聖なるもの」を現代人も見失ってはならないのだ、という説教がつけ加わる、という恰好になっています。
エリアーデがここで混同しているのは、宗教的象徴と実在の間なのです……全体として実在しているのはあくまでも彼らの生活なので、宗教的な象徴そのものが実在しているわけではなく……どうして生活の中のそれらの部分が特に宗教的象徴によって表現されるようになったのか、と問うべきなのです……宗教的象徴が住居をつくるのではなく、そのような住居をつくった人たちがそのような宗教的象徴を考え出すのです。
要するに、その社会の社会構造、権力構造、支配構造、その他あらゆる現実の姿が表現としての宗教に映し出されていくのですが、エリアーデはそういう過程を一切ぬきにして……局部の表象だけをぬき出して拾い集め、「宗教的なもの」と称して、古今東西すべての人類に共通する普遍性、とやらかしてしまうのです。
近代科学の申し子としての宗教学に現実を動かす力はない
近代の克服としての宗教という手品は、こうして、まさにずぶずぶの近代主義の精神の表現なのです。実際は現状に居直りつつ心情だけは異質を求める現代の小市民が、理論的にはまったくの近代主義でしかない発想に頼りつつ、近代を克服すると言って騒いでいるにすぎません……そういうところから抽象的に拾ってきた「宗教」は、現代の現実そのものと取り組むところから出て来たものではありませんから、そのような「宗教」には現代の現実を突き動かす力などはないのです。……近代は確かに克服されねばなりません。しかしそれを克服する力は、生きている人間の生活全体から出て来るので、それを克服する場も生きている人間の生活全体なのです。
宗教的な「非合理性」を担ぎ出して、これこそが近代科学のもたらした退廃状況を克服するものだ、という風にかつぎ出す立場は、実は近代科学の発想の申し子にすぎない、ということがおわかりいただけたと思います。
(関連記事)宗教は現実生活の抑圧や横暴を追認する|田川建三『宗教とは何か』