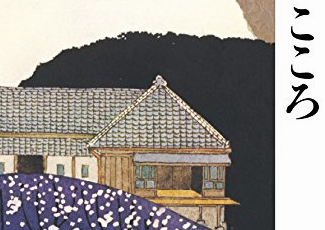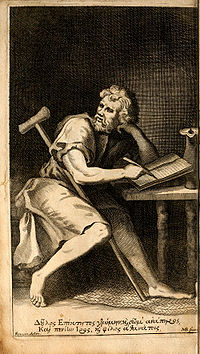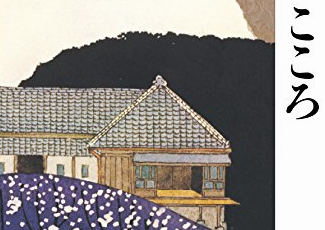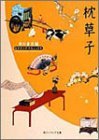プラトンを語るのは、おこがましいことです。
しかし「プラトンについてぼくが知る、わずかなことどものうちのすべて」を語りたいと思います。
「~なことども」「~のうちの」というのは、ギリシャ語翻訳でよく使われるフレーズです。
作品の残存状況
プラトンの名によって伝えられる作品は30以上。
それらはすべて残されている。
これは古代としては異常な現象だ。
たとえばアリストテレスの現在読める作品のほとんどは講義録である。
彼はほかに対話編も書いたとの報告があるものの、残されてはいない。
それに対してプラトンの作品は、ひとつも散逸していない。
偽作の疑いのある作品さえ残っている。
つまりプラトンの名を騙って第三者が書いたと思われる作品さえも残っている。
著作の分類
一般に、執筆年代として三期に分類する。前期中期後期。
分類に際しては、何年に書かれたなど、確実な根拠は少ない。
扱うテーマや内容から、便宜的に分けている。
結末がアポリア(結論が出ない)で終わるから前期とか、
イデアの話が出てくるから中期とか、そういった具合に著作を分類している。
しかしそれは確実な根拠じゃない。あくまで便宜的なもの。
中期だからどうのとか、その他の同じころに書かれた作品と比べてどうとか、
そういう観点から、プラトンのひとつの作品を論じるのは本末転倒というか。
ひとつの作品はひとつの作品として完結しており、
その研究に執筆年代の考慮が入り込む余地はあまりないと思う。
ちなみに、どんな根拠で分類しているのか。
正当性のある根拠としては、たとえば『クリティアス』という作品。
かのアトランティスの物語で知られる作品だが、
冒頭で『ポリテイア(国家)』という別の作品で行われた議論をおさらいしている。
したがって、『クリティアス』は『ポリテイア』より後に書かれた作品である。
このように根拠づけていける。
ただし後期に書かれたとされる作品群については、全く別の根拠がある。
コンピュータを利用した文体分析で、いくつかの作品の語彙の選択や使用法について、
ある種の類似性が見出だされるとされ(詳しくは不明。)、
その他の作品には見出だされないことから、それらが後期作品であると推定される。
参考文献
プラトンについての参考文献は、以下から参照するとよい。
巻末の参考文献が充実している。 また、岩波版プラトン全集にも古いが基本的な参考文献は見つかるだろう。
こんなウェブサイトもあるようだ。
「ソクラテス・プラトン研究日本語文献目録──1975年~1995年」
Japanese Bibliography on Socrates and Plato