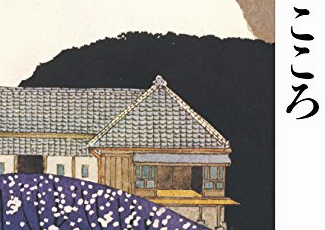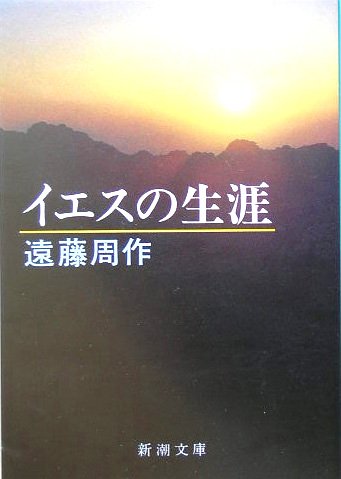牧野信一は、異様な文学者である。
牧野信一の小品集(冊子)を読んでみよう。
『凸面鏡』はかなり初期の作品のようだ。
文字数もおそらく8,000字程度。
下記クリックで好きな項目に移動
凸面鏡のあらすじと冒頭の書き出し
タイトルの「凸面鏡」とは、カーブミラーのような鏡のこと。
顔そり用の凸面鏡というものがあったそうだ。
この作品は、学生の主人公が道子という女性に恋心を抱いていたが、
その女性とは姉と弟のような間柄で、しかも彼女はもうすぐ別の男性と結婚してしまう。
その彼女が、怠惰な主人公の学業や将来を心配しているが、
主人公のほうはつっけんどんな態度をとることしかできないという、
だいたいそんな話である。
冒頭を引用しよう。
「君は一度も恋の悦びを経験した事がないのだね。――僕が若し女ならば、生命を棄てゝも君に恋をして見せるよ。」と彼のたつた一人の親友が云つた時、
「よせツ、戯談じやねえ、気味の悪るい。」、と二人が腹を抱へて笑つてしまつて――その笑ひが止らない中に、彼はその友の言葉に真実性を認めたから、自分を寂しいと思ふ以上に、親友の有り難さに嬉し涙を感ずる、と同時に、「そんなに心配して呉れないでもいゝよ。」と答へ度いやうな安心と軽い反抗とを感じた。それは彼が恋をした最初の瞬間、同時に失恋をしたところの道子を思ひ出したのであつた。一分間の中で、恋をして、失恋をして、さうしてその悶へと、恋の馬鹿々々しさとを同時に感じて、然もその同じ一分間を何辺となく繰り反した「ある期間」を道子の前に持つた事がある、と彼は思つてゐたから、――あの一分間をだら/\に長く延したものを持つた人が、所謂「美しい恋の絵巻」の所有者となつて誇り、あの一分間に感じた失恋を、ちよつと形を違へて(幸ひにも)長く経験した人は痛ましい失恋者となつて自殺することも出来るが……自分は――で、もう、あらゆる恋の経験はして来たのだ、といふ気がしてゐた。この気持が友によく解つたら友は屹度安心するだらう、が何しろその恋なるものゝ形式が余りにはかないので、どうやら言葉で説明したら、この親愛なる友を慰める事が出来るだらう、……と、など彼は考へて居た。
どうだろう。かなり異様な雰囲気を漂わせているように感じた。
凸面鏡の感想と特徴
まず、感じるのは一文が長い。読点を打ってだらだらとつなげている。
そしてダッシュ記号――や三点リーダー……の多用。
主人公が言葉にしがたい自身の思いを、リアルタイムで考えながら書いているような筆致である。
ぼくたちはそれをややこしく・もどかしく感じる一方で、その主人公の呼吸が伝わるような気もする。
次に冒頭の親友の言葉が引っかかる。よく読むと異様なことを言っている。
いくら親友といえど、自分が女なら命を投げ出して君に恋するなどと述べるのは、どんなメンタリティなのだろうか。
そしてそれにうれし涙を感じるという主人公のメンタリティ。見当がつかない。
そして恋という言葉から始まる主人公の思い。
一分間の恋という表現に勢いを得て、「ある期間」「美しい恋の絵巻」というフレーズを持ってくる。
しかしそれが意味する内容は不明瞭である。
この冒頭は現在を表し、このあと道子とのその一分間の恋なるもの、
何度も繰り返された一分間の恋のうちのおそらく最後のものを、回想する。
主人公と道子がどのような関係であるのか。
同居しているようだがそのいきさつは。
そのような舞台設定について、著者あるいは主人公からの説明は一切ない。
かれらの会話から推測するしかない。
事情を知る人に向けて書いたのかさえと思うほどで、これもこの作品の謎めいた雰囲気に一役買っている。
短いがゆえに、説明があまりにも少なく、妙な雰囲気を生み出している。
記号の使い方がネットスラングの先取りをしすぎ
それともう一点。いくつか引用しよう。
(「妾」は「わたし」と読むそう。)
「どうして純ちやんは此頃さう意固地になつたのでせう。妾が何か云ふと直ぐに喧嘩越になるか、ひやかすか……少しも妾の云ふ事を真面目に聞いて呉れないのね。」道子の眼眦は桃色に上気して、もう露のやうな涙が光つて見へた。
「――――」
「まあ、お坐りなさいつてえば!」
――彼は(涙を感じた。)傲然と安坐をかいた。
「――」彼は煙草に火を点けた。
「――」道子は亢奮し切つた声で「純ちやん。」と呼むだ。
「妾はね……妾はもう四五日でこゝの人ぢやなくなるのよ。」道子は泣声ふるはせた。
「――」――
ダッシュの使い方・・・。
特に最後の「――」――
これは奇跡の表現だ。勇気ありすぎる。
言葉にできない気持ちは言葉にしないと、開き直っているのか?
ふつうこんなん書けないよ。
現代でいうとネットで見かけるこれに近いのだろうか。
オレ「」
なんもいえねえ、そんなときに使う表現だ。
トップ画像のポートレートは、小田原市公式サイトより引用させて頂きました。
小田原文学館は、牧野信一はじめ、様々な文学者の足跡が確認できる、おもしろい文学館です。