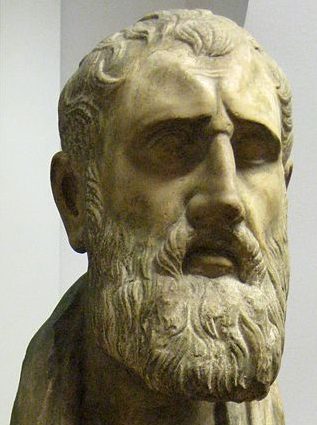斎藤緑雨という天才風刺作家が、われわれに地獄を見せてくれます。
下記クリックで好きな項目に移動
斎藤緑雨の『油地獄』
主人公は目賀田貞之進という書生。
勤勉で評判のよい法学部の学生ですが、ある日の懇親会で小歌という柳橋芸者に出会い、彼女に恋してしまいます。
そのきっかけはおおむね次の通りです。
小歌は懇親会で貞之進の隣に座り、貞之進がお手洗いへ出かけたとき、彼の後ろに小歌が立っていました。
小歌はハンカチを差し出すが、慣れない貞之進はそのハンカチを取っていいのか分からない。
あら儂のではお厭なの、どうせねと推附るようにして渡した時、何とも云えぬ香気が鼻から眼へかけて貞之進はまず眩いた。
ちょっとした思わせぶりの言葉遣いは、芸者にとってはお手の物です。
というか、花柳界とは、そういう思わせぶりな言葉のやりとりや、振る舞い・仕草に、何かしら意味ありげな表現をする世界です。
そういった言葉のアヤだったり、仕草のやりとりは、ある種の記号(コード)というべきものです。
お客さんや芸者は、そのやりとりを互いに理解しながら、その場の特別な雰囲気を楽しむわけですが、書生目賀田貞之進は、この記号をことごとく読み違え、妄想を重ねていくという構造です。
「あら儂のではお厭なの」
この小歌の発した言葉がために、貞之進の勘違いが深まる様子を、少し長いですが引用してみましょう。
(古い文体で読みにくいので、小さくても声に出して読んでみると、リズムがつかめて読みやすくなるかと思います。)
枕に就きは就いたが眠られない、眠られないとゝもに忘れられない、仰向いて見る天井に小歌が嫣然笑って居るので、これではならぬと右へ寝返れば障子にも小歌、左へ寝返れば紙門にも小歌、鴨居にも敷居にも壁にも畳にも水車の裾模様が附いて居るので、貞之進は瞼を堅く閉じて、寝附こう寝附こうとあせるほどなお小歌が見える。これがあるからと洋燈を吹消たが、それでも暗闇の中に小歌の姿が現われて、「あら儂のではお厭なの」、の声がする。術策尽きて夜着を頭からスッポリ被ったがやっぱりいけない、起きて居た時よりは一層激しく肚裡に跳る者があって、或いは急に或いは緩に、遠慮なく駆け廻る。その内目はいよ/\さえて来て、ふと小歌の年齢に考え及ぼし、いつの間にか自分と夫婦になって、痴話もする苦説もする小鍋立もする合乗もする、恐い事恥しい事嬉しい事哀しい事面白い事可笑い事、腹一杯遣って退けたと思うと元の鳴鳳楼の座敷へ環り、「あら儂のではお厭なの」、のお温習がまた始まる。
以来、貞之進は学業に手がつけられなくなり、無理な金の工面を重ねて小歌との逢瀬を重ね、何とか彼女との恋を果たそうとします。
しかし、小歌は当然ながら彼を本気に思ってなどおらず、別の客に落籍されて、その囲われ者となります。
失意の書生、目賀田貞之進は、恨みや悔しさをぶつける先もなく、鉄鍋に油を煮立たせ、小歌の写真を投げ込み、発狂して物語は終わります。
「ひとりで妄想を重ねる」という現代的すぎるテーマ
斎藤緑雨『油地獄』の中では、「あら儂のではお厭なの」という小歌の言葉が、貞之進の脳裏で何度も何度も繰り返されます。
要するに貞之進はこの小歌の言葉一発で彼女にほれ込んでしまうのです。
そして、小歌の言葉の意味が繰り返されるたびに、貞之進の妄想が膨らみ、一方的な思いを募らせていくのです。
あまりに現代的なテーマ(笑)
『油地獄』とは、ウブな男が、思わせぶりな女性の言葉に勝手にすっころぶという悲喜劇と言えるでしょう。
『油地獄』は発表後すぐに評判になり、詩人で評論家の北村透谷が、「『油地獄』を読む」という評論を発表しています。
そこで透谷は、斎藤緑雨を風刺作家であると規定し、その本質を「或一種の不調子、或一種の弱性」と規定します。
一種の不調子とは何ぞ。曰く、現社界が抱有する魔毒、是なり。
一種の弱性とは何ぞ。過去現在未来を通ずる人間の恋愛に対する弱点なり。
まとめると、『油地獄』とは、非モテの男の痛い話なので、現代の男子の必読書です。
作品集はこちら↓(『油地獄』だけなら青空文庫でも読めます。)