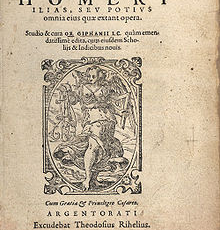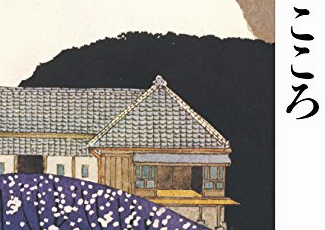英文如来。
ダサいくせに、妙に心に引っかかる。うまいネーミングである。
この異名を持っていた人物は、森田思軒(もりたしけん)。
明治20年代に活躍した翻訳家である。(1861年~1897年)
明治時代、森田思軒のことを知らない人間はいなかった。
文学界や批評界だけでなく、一般にも知られた人物だった。
坪内逍遥や森鴎外や、二葉亭四迷と並ぶ名翻訳家だったのだ。
しかし、このうち森田思軒だけが、現代においてほとんど知られなくなってしまった。
下記クリックで好きな項目に移動
書き言葉に革命を起こした男
森田思軒は、翻訳の文体に大変革をもたらした。
当時はまだ翻訳といっても大胆な翻案や、乱暴な抄訳が多かった。豪傑訳の時代などと言われる。
しかし森田思軒は世間から「周密文体」と呼ばれるほど原文に忠実な訳を心がけた。
今で言う直訳だ。
直訳なんて当たり前? そうでもない。
明治の時代に直訳調の文体で翻訳を書くというのは異例の事であった。
つまり、原文に忠実に訳す方がむしろ異例なことだった。
俗に翻訳調と言われる文体は、現代でも普通に使われている。
読みづらくて下手くそと言われる翻訳文のことである。
現代に通じる、外国語翻訳文の骨格を形作った日本人は、3人いる。
- 森田思軒(英語)
- 森鴎外(ドイツ語)
- 二葉亭四迷(ロシア語)
この3人だ。
極端に言えば、森田思軒の周密文体すなわち直訳調の翻訳があったからこそ、現代における書き言葉が発達した。
私たちがレポートや報告書で無意識に書いている堅苦しい書き言葉。
明治時代の森田思軒の翻訳のおかげであると言える。(言い過ぎかもしれない。)
森田思軒の翻訳~直訳と意訳のルール
明治の翻訳者たちは、和漢洋3文体をうまく融合させることに心を砕いた。
翻案だろうが超訳だろうが、大和言葉や漢語漢文に直せるところは直す。
あるいはカタカナ語をそのまま使うこともあった。
その傾向は、とにかく外国語(ほぼ英語)と日本語の垣根・障壁を取り除くこと。
読者にとって読みやすい文章を練り上げることだった。
だが、森田思軒だけは違った。
ルールその1 異質の思想を「異質のまま翻訳する」
日本語と外国語は言葉の順序も違ければ思想も違う。
日本語にない単語が外国語にある。逆もまたしかり。
日本語にとって外国語は、異質である。
その異質な外国語をそのまま日本語にすると違和感がある。
- 「こなれていない」
- 「訳文が生硬で読みづらい」
などと評価されることがある。
しかしあまりにもこなれた日本語では日本語と外国語の間の違いが埋もれてしまう。
その差異がなくなってしまうことで、外国語独特の考え方が見えなくなってしまうという弊害もある。
「違っているのを、違っているまま、幾分か見せたい」
これが森田思軒の書き残した言葉である。
ルールその2 直訳と意訳の問題
直訳に対する言葉として、意訳という言葉がある。
意訳とは要するに原文で意味する内容を読み取った上で、それを読み易い自国語に変換していく作業である。
直訳調では日本語としてぎこちないから、意訳によって読み易いこなれた文体に変換するという作業である。
この直訳と意訳の組み合わせによって翻訳はできあがる。
ただし意訳にもデメリットがある。
日本語としてこなれすぎていること、違和感がなさすぎることが、逆に問題を発生させることもある。
以下の抜粋は、森田思軒の翻訳観がよく現れている。
難しいようで実はたやすいことで、ただそれだけのことのできるのは、いわば翻訳者の普通の資格で、
少し心を翻訳に用いるという者ならば、今一歩進めてそれより以上のところに骨を折ってみなければならないものと思います。
ルールその3 意訳しすぎの問題:共同訳新約聖書
話は森田思軒から逸れるが、新約聖書学者の田川建三という人がいる。
彼は「翻訳書の誤訳」について、いくつか論考を書いている。
上記で確認した森田思軒の翻訳観を、より明確に理解できると思う。
田川建三によれば、「異質の考え方・異質の思想」に出会った時に、
それを「異質のまま理解し、尊敬する」という姿勢が必要である。
そのような姿勢がないとどうなるか。
異質なものに出会った時にそれを理解することができない。
翻訳者が無意識のうちに抱えているイデオロギーが、その翻訳中に紛れ込み、露出するという。
田川建三は、新約聖書の共同訳を意訳しすぎであると、厳しく批判している。
共同訳とは、新共同訳の前身になる訳で1970年代に出た聖書の翻訳である。
この共同訳というのは悪名高い翻訳と言われている。
共同訳の新約聖書ではこんな1節がある。
「ただ神により頼む人々は幸いだ」
これがどの部分聖書のどの部分か、分かるだろうか?
これはマタイ福音書の山上の説教の冒頭の有名な句である。
一般的には「心の貧しいものは幸いだ」と訳される箇所だ。
この箇所、もう少し正確に直訳するとすれば「霊において貧しい人々」となる。
この霊において貧しいということは、聖書の伝統においては従順な姿勢、ひたすらへりくだる姿勢を意味するそうだ。
つまり、「ただ神により頼む人々」というのは「霊において貧しい」というその意味合いだけを拾い上げただけの意訳。
「霊において貧しい」という日本人にとっては異質な考え方・異質な表現を、消し去っている。
「心の貧しい人」では、なぜダメなのか?
共同訳の翻訳観によれば、日本語では「貧しい心」とは「さもしい心」しか意味しないという。
だから、山上の垂訓の冒頭な句は「神により頼むものは幸いだ」という風に翻訳したのである。
これは日本語の読者をバカにしてかかった発想であると、田川建三は指摘する。
新約聖書を読んでいて、イエスの言葉で「心の貧しいものは幸い」という文に接したときに
「さもしいエゴイストが幸いである」などという意味に勘違いして受け取ることなどまずありえない。
もしそういう勘違いをしないようにと、親切心を働かせてくれるのであれば別にやり方がある。
訳文そのものを変えるようなことはしてはいけない。
そうではなく、コメントや注釈・解説の形で説明を付加するべきだ。
「これはエゴイストの意味ではなく、神により頼むという意味なのですよ」
と解説を入れればいいだけのことである。
田川建三は、翻訳を通して異質に出会う権利が読者にはあると言う。
心の貧しいものは幸いと書いてあれば、読者は新約聖書の世界では「貧しさはむしろ積極的な価値として評価されているのだな」と発見することができる。
異質の文化の書物を読むにはこの発見が重要なのである。
まとめ:森田思軒を見直そう
以上、やや極端だが、翻訳における意訳の弊害を例示した。
一発で理解できるような、こなれた読み易い日本語に直すのは、翻訳者の腕の見せ所である。
しかし、原典が持ち合わせていた表現や内容を歪曲する可能性が、翻訳には常にある。
今までつらつら書いてきたこんなことは、少しでも翻訳に関心がある人にとっては、常識にすぎないと思う。
しかし、すでに明治の20年代に、森田思軒がこの問題について語っていたのは、あまり知られていない。
明治初期の翻訳家が、すでに外国語と日本語の差異に一定の考え方を提示しているという事実は、おどろくべきことである。
そして、直訳調の文体を作り出したということも。
当時は直訳や意訳などという言葉さえなかった。
翻訳とは名ばかりのエンタメ性、読者受けだけを狙った大胆な改変が横行していた。
そして読者もそれが外国文学、それが普通の翻訳、という風に受け取っていた。
森田思軒は、近代日本語の創出者の1人だった。
森田思軒の翻訳が読めるのは、こちらの岩波文庫。